なんと心が狭い人間なのだろうと思った。泣きながら、何処か人気のない場所を探して廊下を行く。幸運なことに、それは地上で言えば夜がいよいよ深まる落ち着いた時間帯であった。それゆえ、人目を避けて廊下を行く人間を見つける相手はどこにも見当たらない。どこかの部屋から聞こえる、楽しそうに談話する仲間の声。仕事場で仲間を労う優しい上司の声。普段なら何と言うことはないそういった光景が、今はわたしの心を深々と突き刺した。そんなはずはないのに、わたしは彼らにとって必要のない人間なのかと思う自分を止められなくて涙が落ちる。最近の自分の状態があまり安定していない事には薄々感づいていたが、それでも心の、いや、体の奥底から吹き出してくる深く暗い感情は、おおよそ目も当てられないほど酷いものであった。幸せを見ると、自分が嫌になる。決して自分が不幸なわけではないのに、それでもわたしはそこに無意識の優劣を生んでしまうのだ。ばからしい、そう思って笑い飛ばすことができる人間は幸せ者だ。世の中には確実に、彼らより遥かにそうすることの苦手な人間がいるのだから。しばらく彷徨って、やっと人の気配すらしなくなった頃、わたしはわたしが、誰もいない場所を探しながら、実際は誰かに出会うことを期待していることに気が付いた。心臓の温度がぐんと下がる。悲劇のヒロインを気取りたがるどうしようもない自分に腹が立って涙が息を詰まらせた。もはや落ち続ける気持ちが重すぎて、わたしはその場にうずくまる。何と甘えた人間だろう。わたしは甘い蜜さえ吸えれば他はどうでもいいと思っている浅ましい女で、その蜜を吸う権利が欲しいあまりに、頑張っている振りをしてそれを努力と呼び、さらには他人に見劣りしたくないと思うプライドだけで自分を守ってきた薄っぺらな人間だったのだ。だからいつも他人が羨ましかった。自分以外の人間はみんな真面目に努力ができるのだと羨望した。自分以外の人間だけは自らの力で美しく輝いているのだと怨望した。そうしてわたしは卑屈になって、ついに自分の殻に閉じ籠ったのだ。この発見は、とても大きな衝撃と引き換えにわたしの涙を奪っていった。止まらなかった涙が止んですぐ、わたしは熱い目を両手で冷やしながら、ゆっくりと立ち上がって壁に凭れ掛かる。しかし、周りと自分を隔離していたのは他でもない自分自身、やっとその答えに辿り着いた時、わたしはもう一度泣きそうになった。なぜなら、わたしが本来戦わなければならないものは、空想的な孤独や体の奥底から生まれ来る暗い感情ではなく、膨れ上がったこの自尊心だと、気付いたからだ。言い様のない恐怖が、そこにはあった。しかし、再び涙が零れる前に突然の優しい声がわたしを襲う。
「こんなとこでなーにしてんだよ、」
「...ロックオン」
「"ニール"」
「でも」
「2人っきりだ、誰も聞きゃあしないさ」
彼が自分から、本名を呼ぶように言ってくることは珍しい。滅多にない事態で思わずわたしがニールの言葉に従って名を呼ぶと、歩み寄ってきた彼はそれに満足そうに頷いて、その手をわたしの頬へと伸ばした。少し冷たい指先は、熱を持った頬に気持ち良い。緑色の綺麗な双眸が、わたしの様子を注意深く窺っているのが、手に取るようによく分かる。ゆっくりと、瞬きをする。あまりの優しさに甘えたい気持ちが募って泣きそうになっても、それでもわたしが泣かないでいられるのは、恐らく彼が傍にいてくれるからなんだろう。
「こんなになるまで泣いたのか」
「....あたしが泣いてるの、知ってたみたいな言い方ね」
「甘く見るなよ。これでも俺はお前のこと、結構知ってるんだぜ」
「....じゃあ、こうなる前に何か言ってくれたらよかったのに」
「そうしたら、いつか、きっとまたお前は同じことで立ち止まる....だから言わなかった。でもな、」
これだけは覚えていてもらおうか、そう言って、ニールはわたしの額にひとつキスを落とす。わたしは何度も味わったその感覚に、目を閉じた。慰めてくれる時、彼はいつもこうしてわたしを抱きしめるのだ。柔らかな想いがゆっくりとわたしの中に入り込んできて、色んなものを包み込んでくれる気がした。彼は柔らかい。愛情も、笑い方も、選んで与えてくれるその言葉も、ぜんぶ。わたしはその柔らかな感情に包まれて、頷きながら目を開ける。
「なあに」
「何も言わないからって、そいつが何も見てない訳じゃない」
「...ニール」
「言ってること、分かるか」
「うん」
「...何かあったら助けてやるよ。だから」
「悩んで泣いて、笑って.....お前はお前らしく、全力で生きてみろ」
人気のない真っ暗な部屋の中で、ゆっくりと、瞬きをして、わたしは視線を外へと向けた。窓一枚隔てた向こうには、今日も相変わらず闇の渦のような世界が広がっている。ふと、視界の隅で煌々と光るものがあってそちらへ視線をやると、その光源は枕元に置いた携帯の着信表示の明かりであった。浮かんでいた涙を拭って、わたしはその指先で着信を受け入れる。少し冷たい指先は、熱を持った頬に気持ち良かった。
「いえ、寝てましたが泣いてません大丈夫です....わかりましたすぐに行きます」
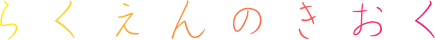
021009
(その痛みを忘れるな)