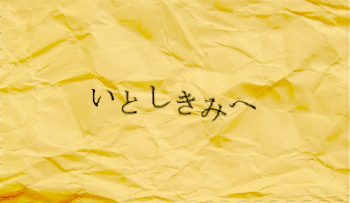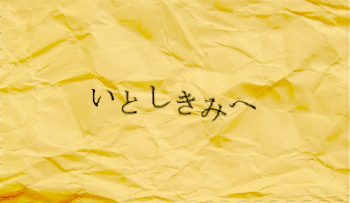彼女には、どこに行っても顔見知りがいた。戦況オペレーターはもちろん、食堂に行けば調理師、医務室に行けば看護師、格納庫に行けば整備士。ガンダムマイスターから、清掃員まで、その数は挙げていけばきりがない。つまり、彼女は出会った人間とはすぐに打ち解ける、何ともオープンな心の持ち主なのである。そしてそんな彼女とは正反対の内気な僕は、そんな社交的な彼女がとても好きで、そして同時にとても憧れてもいた。彼女の周りにはいつも感情が溢れているのだ。その空気はまるで、様々な色が弾けて織り成すパレードのように、賑やか。これは僕にはできないことで、いつも僕は心底彼女を褒め称えた。しかし、そのオープンな社交性も、一歩間違えば大変厄介なものに成り代わる。例えばどんな時かと言うと、今。
「捕まえた」
「ライル!離してよ、もう」
「おまえ、こんないい体してんのに、一人しか男を知らないなんて勿体無いぞ?俺が色々教えてやる」
「いいですもう足りてますから...ってか、なんでわたしが一人しか知らないって知ってんの」
「そりゃあ俺は情報通だからな、しかし、燃えるね」
「え?あ、ち、ちょっと今胸触ったでしょ!」
ミッションから帰艦してシャワーを浴びて出てきた僕を出迎えたのは、果たして何だったのか。夢か、幻か、現実か。少し考える。そうしてすぐに、そのすべてにおいて答えはノーだと思った。これは、夢でも、幻でも、現実でもない。何とも純粋な、悪夢だ。僕はそっと顔を覗かせて、2人を見た。ロックオンが後ろからを抱き締めている。どれだけ強い力で引き寄せているのか、のお腹に回された男の腕がやけに彼女の胸を目立たせていた。触れて欲しくない、と思ったけれども、そんなことを男らしく言う勇気がない僕は、じくじくと痛む胃を恨んで、この悪夢が早く消えてくれればいいと願いながら瞬きをした。あの柔らかさは僕しか知らない。僕以外は知らなくていいんだ。無意識にそう思った僕は、そうして自分自身の醜さに改めて失望する。なんて、浅ましい男なんだろう。
「ライ......」
声が途切れて、突然に訪れた、不自然な沈黙。まさか、と訝しんで再び2人を見遣ると、それは容赦なく僕の両目に映り込んだ。2つあるはずのシルエットが重なっている。視線の先で、不意に黙り込んだの唇が、キスをしていたのだ。何だか前にもこんな状況があったような気がして、僕は心底嫌気が差した。キスを許しているに、ではない。何ら進歩のない自分に対してだ。その時は確か、は刹那と言い争っているだけだったけれども、あの時も、僕は勇気がなくて、ただ、苦しくなる胸に息を詰めているだけだった。これは、何だ?神が与えた試練だとでもいうのか。そんなもの、用意するくらいの暇があるのなら、とっととこんな世界をどうにかしてくれ。長い沈黙を破って、聴いたことのないの声が、微かに辺りに広がる。僕はぞっとした。なんて声を、上げさせるんだ。痛む胃に従って避けていた視線を、もう一度だけ2人に向けると、酷い嫌悪感が僕の中で鮮やかに輝きだした。
「ロックオン!」
「...ア、アレルヤ!」
「おっと、ヤバイな、王子様の登場か」
「を、離して」
「.....嫌だと言ったら?」
ロックオンがもう本気ではなくて、単にからかっているだけだということは、僕にはすぐに分かった。視線はロックオンに据えたままで、ライル、と叱責するように名前を呼びかけた、の口元を片手で覆う。何度、きみは他の男の名前を呼ぶ気なんだい。
「あなたに、僕の要求を拒否する権利は、ないと思う」
「あーあー、わかったわかった、冗談だ、返すよ」
「ありがとう、ロックオン」
「だが、ようく注意しておくんだな、敵は多いぜ?」
を引き受けて、僕は一度だけ、僕よりも若い青年のことを思い浮かべた。そうして胸中でひとつ溜息をついてから、背を向けたまま軽く手を振ってその場を後にするロックオンを見つめる。百戦錬磨の彼が、敵の一人ではないことを、心底祈りたい。彼が敵ではありませんように、彼が敵ではありませんように。念入りに、ついさっき暴言を吐いたばかりの神様にそう祈って、僕はと向き合った。途端、思い出したくない光景が脳裏にちらつく。居た堪れなくなった僕はぎゅうといつもより強く、を抱き締めた。心配で心配で心配で、息が出来なくなりそうだ。
「」
「.....アレルヤ?」
いつもと様子の違う僕に勘付いて、は不審げに僕を見上げた。その目は随分と心配そうだったけれども、その視線を満足に絡め取ることもせずに、僕は半ば強引にの唇を塞ぐ。浮かんでくる光景を掻き消すように深くまで求めて、僅かに逃げようとするの舌を捉えて、腰に回した腕に力を込めた。そうしないと、じきにが立てなくなる。
「...ふ、...あ、」
「まだ」
が僕に縋りつくのを知りながら、僕は再び彼女にキスをした。わざと浅く何度も繰り返せば、聴き慣れたの声が耳を擽る。それに少し安心してそっと唇を離すと、完全に「女」の顔をしたが黙って僕を見つめていた。なんだか急に切なくなって、少し息の乱れたの唇を指先で撫でる。するとすぐに、がやんわりと微笑んだ。こんな時、僕はいつも上手く感情をコントロールできない自分が子供みたいに思えてとても嫌になるのだけれど、きっとはそれを薄々察してくれているのだろう。
「アレルヤ....少し、落ち着きなさいよ、心配なんていらないから」
「」
「なに?」
「僕はあんな声、聴きたくなかった」
「ごめん」
「キスも、させないで欲しかった」
「ごめん」
「」
「うん...好きよ、アレルヤ」
額に優しい温度が触れる。突然に届けられたその音はどうしようもないくらい自信に満ちていて、僕の抱える劣等感や罪悪感や嫌悪感をすべてどこかへ追いやった。といると、いつもそうだ。はいつも、僕の中の苦い感情を強引に押し退けて自分の居場所を作っていくし、僕はというと、そんなに器用でもないから、彼女のことを考えるときはいつだって一杯一杯。劣等感とか罪悪感とか嫌悪感とか、そんなものを考える余裕など、とてもじゃないが作れやしない。それに、彼女に出会って、僕の世界は非常に複雑に入り組んでしまった。毎日毎日、考えることなんてたくさんある。おかげでどうすればいいのか分からずに困り果てることも多いけれど、しかし、そんなに悪い気もしない。人間って、ほんとうはこんなものなんだろうと思うから。
「そうだ、お詫びにいいこと、教えてあげようか?」
「いいこと」
素直に言葉を繰り返した僕を見てにやりと笑ったに、僕はとても嫌な予感がした。彼女がこうして笑うときは、大抵僕をからかおうとしている時で、そうしていつも、僕は彼女に申し分なくからかわれるのだ。不意には僕の手を掴んで、彼女のお腹にその手を宛がった。ああ、今日は一体何をするつもりなんだ。
「ここには、アレルヤしか、入れないのよ」
「.....!き、きみって人は!」
「また赤くなってるし....いっつも喜んで抱くくせに、そういうとこ、自分で矛盾してると思わないの?」
「、いいから、もう!」
面白そうに笑うの腕を引いて、僕は火照った頬のままで会話を誤魔化すように廊下を歩き始める。笑い続けるに少しむっとして、知らない振りをしてやろうと思ったけれども、しかし彼女がその腕を僕の腕に絡めてきたので、僕は仕方なく視線を向けた。そうしてどこか嬉しそうに笑うを見つめて、諦めたように笑い返す。何故か僕は、僕を真っ直ぐに見上げてくる、僕よりもずっと弱いはずの女の子に対して、勝てないな、と途方もなくそう思った。
「まだ、怒ってる?」
「ううん」
「じゃ、怒ってた?」
「少し」
「きらいになったとか?」
「まさか、それはないよ」
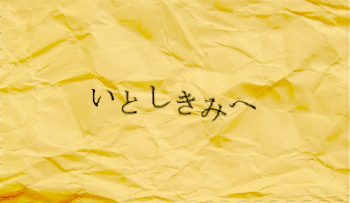
112008