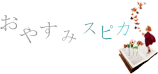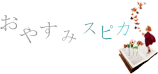
すきだ、という最後の言葉だけを鮮烈に刻み込んで目が覚めた。額を冷たい汗が滑り落ちる。唇が乾いてかすかに震える。およそ夢とは思えぬ強烈な画に衝撃を受けた心臓がずきずきと痛いほど鼓動して、すこしばかり目眩がする。しかしそんな画が果たして地獄の光景であったのか、はたまた天国の光景であったのかは、わたしには到底判断できなかった。ただただ、思い出すには容易すぎるその脳裏の記憶に、再びわたしは凍えるように息を吐く。それは午前五時の、まだ朝早い時間であった。隣から、規則正しい、しかしまったく違う規則に従う寝息がふたつ、微かに耳に滑り込んでくる。ゆらゆらと僅かな揺れを帯びながら進む船の中はいつもと変わらぬ平穏で充ちている。わたしは自身にそう言い聞かせながら、汗ばんだ着衣を脱ぎ捨てて新しい衣服を乱雑に頭から被る。どうせシャワーを浴びるまでの間身に纏っておくだけのものだ。そう思って一度も鏡を見ずに部屋を出た。白い淡白なシャツが、動く度に幾度も肌をくすぐった。甲板に出ると、ちょうど朝陽が水平線をじりじりと焦がしているところで、東の空が薄明かりに包まれているのがよく見える。昇ってくるのも、あと十数分のうちであろう。誰に頼まれるでもなくわたしがそう予測をつけて、冷えた空気に肺を浸して辺りを見回せば、船首の上にぽつりと浮かぶ小さな人影が見えた。それは麦わら帽子を片手で押さえながら、大きく欠伸をして何の気なしにこちらを向く。常に麦わら帽子を手放さない、その人間こそが、この船にとってのかけがえのない船長であった。彼はわたしの存在を目に留めると、ゆるゆると人懐こい大きな笑顔で、おーいと言って手招きをしてまた前を向く。しかし、その純粋な笑顔に足がすくんだわたしはそこから一歩も動けない。なぜなら、それが、天国か、地獄かで見た画に見事に一致する光景であったからだ。しかし驚愕するわたしの事情など微塵も知らぬ船長が、ひょいひょいと段差を乗り越え距離を埋めてやってくる。そうしてわたしの指先の微かな震えに気が付くほど近付いた船長は、言い掛けた言葉を仕舞って一度、黙ってわたしの双眸を覗き込んだ。笑顔など微塵も窺えぬ真剣な表情で、彼はわたしの両手を掴む。
「お前、寒いのか?」
「ううん」
「でもすげえ震えてるぞ、風邪かもしんねえしチョッパーに診てもらおう」
「違うの、大丈夫、ルフィ気にしないで」
掴んだ手を引いて船医の許へと向かおうとした船長を引き留めて、わたしは一度だけ首を左右に振った。幸運なことに、それで船長の足取りは止まったが、しかし放されることのない手が彼の意思を告げてくる。ずきずきと、またわたしの心臓が青冷めた。
「ちょっと夢見が、悪かっただけなの」
「夢?」
「ルフィの傍で死ぬ夢を、見たよ」
「え」
一瞬頓狂な声を上げて、目の前の船長が驚きに目を瞠った。わたしは小さく苦笑しながら視線を落とす。言ってみれば何でもないただの夢なのに、この生々しさは何だろう。もしかしたら、あれは予知夢で、近々わたしは本当に死ぬのではないかと、思わずにはいられない。だがあんな風に好いた人にすきだと言われながら死んでいくのなら、きっとそれは悪い死に方ではないのだろう。最期を愛しいものに看取ってもらえるのだって、この海の上では随分と幸運なことだ。なんだ。考えてみれば、全然悪い死に方ではないじゃないか。わたしはひとつ、悪くない答えを導き出すと、半ば必死にその結論にしがみついた。余所を向いたら、死に対する巨大な恐怖に体ごと持っていかれるような気がした。確かに、夢での死に方は幸せな死に方だと言えるだろう。だが、だからと言って死んでもいいとは思わない。死にたくない。死が怖い。そう思う度、夢の温度が甦ってわたしの指先を容赦なく冷やした。いよいよもって体が震えそうな気がしたが、不意に強く抱き込まれて震えは起こらず代わりにわたしの息が詰まる。たった一枚羽織っただけのシャツ越しに伝わる酷く温かな人肌の温度が、泣けるほど心地好かった。
「おれが傍にいてお前が死ぬなんて、そんなバカな話があるか」
「ルフィ」
「絶対に死なせたりしねえから、心配すんな」
「...うん、そうだね」
「ああ」
しししと笑って再び強くわたしを抱きしめると、船長はわたしの震えの収まりを確認して今度は肩を組みながら歩き出す。彼の足取りは元いた船首に戻るようでもなかったので、どこへ行くのかと思ったが、すぐに鼻先を擽る芳しい匂いに気が付いて小さく笑みが漏れた。
「だいたい腹減ったまま寝るからそんな変な夢見るんだ、サンジに飯もらいに行こう おれも腹が減った」
「ルフィそれ...一番最後が本音よね?」
「んなこたぁねーよ」
そうしてわたしと船長が笑いながら並んでキッチンの扉を潜る頃に、東の海からようやく朝陽が顔を出す。甲板の下の寝室からは、徐々に起き出す船員達が織り成すいつもと変わらぬ賑やかな朝の気配がした。