茫然自失とは今の状態のことなのだと、戦渦を見つめながらわたしは思った。何も考えられないのに、感情だけが溢れて喉に詰まっている。声が出るはずの唇の合間からは荒い息ばかりが滑りでて、その冷たさに唇が震える。両の目からは落ちても落ちても溢れて止まらないなみだが生まれてくる。平和な世の中を、人々は望んでいたはずだ。幸福な世の中を、わたしたちは望んでいたはずだ。そうしてそのために、誰もが一所懸命に生きてきた。それなのに、無理な変化を強いられたこの世界は、その努力を労うどころかすべてを飲み込んで掻き消していった。それは、ほんの一瞬のことでしかなかったのに、一生続く悪夢のような出来事であった。こんなにも血生臭い方法で勝ち取る幸福など、一体誰のためになるだろう。わたしは徐々に遠くなる、未だに戦渦の収まらない湾岸を見つめようと瞬きをした。しかし何度でも溢れてくる涙ですぐに視界が霞んでしまう。悔しかった。目の前で倒れていく人々がいても、涙を流す人々がいても、何が正しいのかを肌で感じ取っていても、何もできない。何かしてやりたいと思うばかりで、部外者の自分には何一つできることがない。不意に、「おまえは海軍に打って付けの気性だな」と、背後の扉に寄り掛かって同じ方向を見つめていた男が嘲笑うかのようにそう言った。もちろん、彼の言葉は皮肉だった。思うばかりで何も出来ない人間なんかが海軍の役に立つわけがない。しかし同時に、わたしはその言葉に潜む優しさにも気が付いていた。わたしは背後に立つ彼を振り返る。相変わらず世界は涙で歪んで見えたけれども、それでも彼がこちらを見ていることくらいは容易に判別できた。遠くで、大砲の音がする。瓦礫の落ちる音がする。しかしわたしはその音に背を向けて、その日初めて涙を堪えて、目の前の男ただ一人のためだけに微笑んだ。ああ、わたしたちの望む幸福というものは、きっとこうしてたくさんの人々を飲み込みながら育っていくのだ。
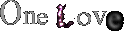
042710
(Never have, never will.)
![]()