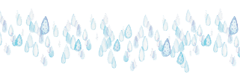夜の間、はずっとエースに触れていた。触れている、というよりかはしがみついていると言った方が正しいくらいに、はエースにきつく抱き付いてその肩口に顔を埋める。大きな船の片隅にある、その小さな部屋では、ちらちらとランプの火が油を食らっては揺らめいていた。エースは黙ってそれを見詰めている。そうして、綺麗だな、と思う。昔、禁断の実を喰らって特異な体質になって以来、触れたところでその熱さは解らなくなったけれども。懐かしいような、空想のようなそれの熱を思い描きながら、緩やかに瞬きをする。腕の中にいるは相変わらずだ。真夜中過ぎにが目を醒ましてから、二人はずっとこうして抱き合っていた。ベッドの上で、立てた枕に背を預けながら、エースは自分に跨がったの柔らかな太股に触れる。そこから少し掌を上に滑らせると、彼女の腰の辺りに丁度掌と同じくらいの大きさの傷がある。いつか、貪るようにを食らってエースが付けたその傷は、こうして生涯消えぬ火傷となって彼女の肢体に刻まれている。それに触れる度に、エースは、申し訳が立たない、と思った。しかし、それと同時に極めて愛おしい心地もした。が呻くように声を漏らして、更にエースに身を寄せる。ゆっくりとエースがその背に両腕を預けると、はついにその顔を上げて、目を醒ましてから初めてしっかりとエースの両目を見詰めた。その目は幾らかの涙に揺らぎながら、紛うことなき狂気を孕んで彼を捉える。ああ、欲情しているのだな、とすぐにエースは気が付いた。その身に一生消えぬ傷を与えられながら、それを与えた男と幾度も危険な境地へ向かいたがる目の前の女は、大概狂っている。微かな呼吸が吐き出されるのを聴きながら、エースは静かにを見詰めた。すると、丁度彼女の傷に触れた時のように、手に余る感情が再びエースの胸の内を占拠する。それはまるで、ちらちらと揺れるランプの火が、いつの間にか体の中に燃え移ったかのようであった。きっとの目に映る自分も、自分の目に映る彼女と同じように見えているのに違いない、とエースは思った。不意に、少し不安定なの声が森とした部屋に満ちる。瞬きの度に透明な涙を落としながら、は、好き、とだけ呟いた。自分に対するその感情が彼女の中の何より強いものだと知っているエースにとっては、まるで欲望など欠片もないかのように響くその一言でさえ、劇物に等しいものであった。そっと額を合わせたお互いの、その少し速い呼吸が、真夜中の部屋に混じり合う。エースは目の前の裸体が傷付かないことばかりを願って、幾度も躊躇うように口付けをして、幾度も零れるの涙を拭ったけれども、ついに決心したかのように、好きだ、とだけ呟くと、ちらちらと揺れるランプの火を吹き消した。相変わらず、ランプの火の熱さは分からなかった。それでも、エースは触れたの涙の温度を知った気がした。
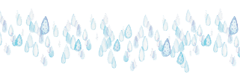

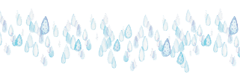
091310
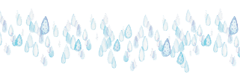
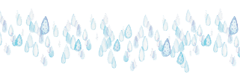
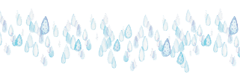
![]()