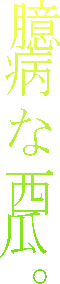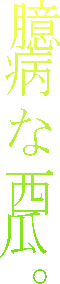そうしてとうとう に赦された言葉は少ない。
しかし神田はそ知らぬ顔で、彼女の言葉を待っていた。
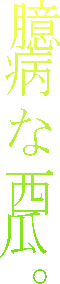
「…今、何て?」
「………俺とマリとデイシャは明日、本部へ向かう。もうここへは戻らない。そう言った。」
辺りに無造作に広がって緩やかに風に吹かれている木々の、その幹からけたたましく音が生まれる。
ミンミンゼミが鳴いている。ヒグラシが鳴いている。
そうして熱い太陽が木々や地面や海や村、果ては二人の指先までを照らし上げていた。
先日までの雨が嘘のようだ。
まだ少し残る地面の上の小さな水溜りの上で、 アメンボが軽やかにワルツを踊っている。
――はただ、立ち尽くしていた。
何となく、最近の元帥と三人の妙に秘密めいた言動は気になっていたけれども、それがこんな現実を示唆するとは思わなかったのだ。
兄弟子は去るという。
それも明日、突然に、永遠に。
本部に行ったら完全にエクソシストに登録されて、二度と「外」へは戻って来れない。
知らないフリも、無かった事にも、出来ないのだ。
死んだってその痕跡は残らないし、本人の意思とは関係無しに任務があれば飛ばされる。
それは、紛れも無く兄弟子である彼の嫌う束縛だというのに
なぜ。
そう考えて、はふと自嘲気味に笑った。
何を馬鹿な事を考えているんだ、そう、脳内で嘲る。
元帥の弟子になったのはエクソシストになるためで お遊戯や暇つぶしでは無い。
自分だっていずれは一人前のエクソシストになって世界を駆け巡るはずだ。
「そっか、…良かったですね、やっと、一歩目ですよ」
「……ああ」
「マリ兄さんは」
「元帥と話してる。」
沈黙が流れる。
重くは無い。
だけど それはそれで厭だと、は思う。
神田はじっとを見つめている。
何か言うのかと思ったが、これ以上神田が何を言う必要も無い事に気が付いたは再び嘲る様に嗤った。
神田はの気持ちを知らない。
好きだから惹きとめて居たいということ、惹き止めたくても勇気が無いこと、勇気が無い自分を嘲笑うしかないということ。
泣き出したいということ。
「……どうぞ神田兄さんもお気をつけて。」
「ああ」
「じゃあ、…わたしはまだ 修行が残っているので、」
そういっては半ば逃げるようにその場を去った。
ヒグラシが鳴いている。梢が木霊していく。
じわりと陽に照らされる首筋に熱が浮いた。
そうして神田から離れるほど、の世界が曖昧になっていく。
最初の一粒が落ちると、あとはもうどうしようもなかった。
世界はどれぐらい広いんだろうか。
人生はどれぐらい長いんだろうか。
出来れば、世界はわたしと彼が出会える狭さであって欲しいと思う。
そうして 人生はわたしと彼が愛し合える長さであって欲しい。
小一時間経って 散々泣いた後、は河原で足を水に浸しながら物思いに耽っていた。
その目は止まらない川を眺めている。
不意にが腰を上げて、そうして踵を返して来た道を戻っていく。
世界はどれぐらい広いんだろうか。
「あ、、お前もこっちに…」
「神田兄さん」
「………。」
「…お話が、あります」
そういってくるりと背を向けて、は元帥達から離れる。
少し目を細めた後、同じように神田もの後を辿った。
「二人とも…喧嘩は駄目だっていったのに…ねえ、マリ?」
「大丈夫ですよ。…元帥、もう一つ訊きたい事があるんですが…」
声が遠退いていくけれど、後ろを辿る足音は止まない。
は先程の川が遠目に見える程度の場所で足を止めた。
酷く暑いのはきっと、緊張の所為だ。
ちらりと川を眺めて そうしては顔を上げる。
「神田兄さ」
「知ってるか」
の言葉を遮った神田に、はその双眸を瞠った。
彼にはもう何も言う事は無いはずだ。
一番大事なことはもう言い終えたのだから。
そう思いつつ、は口を噤んだ。
神田がこの話を知っているかと言ったからだ。
「ある人間が、庭で西瓜を食べた。そうして数日後、そこに芽が生えているのを見つける。…西瓜の芽だ。」
「…何ですかその話、は…」
「そのうち、自分の飛ばした種が成長してゆくのを、その人間は知らぬ間に心待ちにするようになる。」
は訳が判らない。
神田はその物語を終結させる為に、一度噤んだ口を再び開いた。
木陰がまるで何かの生き物のように ゆらりゆらりと影を揺蕩わせている。
「けれど人間にはどうしようもない。成長を早める事も、しっかり実を結ぶかどうかも、西瓜次第だということだ」
「………神田兄さん?」
「それで?お前の話は、」
「あ…わたしは、」
生温い風に息を詰める。言葉を途切れさせてしまった。
そうしてとうとう に赦された言葉は少ない。
しかし神田はそ知らぬ顔で、彼女の言葉を待っていた。
「………あの」
ミンミンゼミが鳴いている。ヒグラシも鳴いている。
まだ少し残る地面の上の小さな水溜りの上で、 アメンボが軽やかにワルツを踊っている。
行かないで欲しい。
会えなくなるのが怖い。
「……っ……す き です……行かないで…」
どうして時は進むんだろう。
は俯いて泣きながら恨めしそうに川を眺める。
居心地がいい瞬間で止まっていられたら、とても幸せなのに。
「………俺の行動を束縛するなら 俺はお前には答えない」
「…………………」
神田の声は 緊張と感情で高まったの体温をいとも容易く冷やす。
それでも、は零れてしまった涙を殺して顔を上げた。
その目は 紛れも無く、止まらない川を眺めていた目だった。
「…最初に わたしの気持ちに対する答えを聞かせてください」
「………嫌いなら、お前の話なんて聞いてねえよ」
神田は目を細めて、ふいと視線を水溜りに移した。
は声が出ない。
喜びよりも驚きの方が早くて、涙が滲む事は無かったけれども、それもきっと時間の問題だろうと思う。
「だがお前が、俺の行動を妨げるなら」
「じゃあわたしを、…わたしも連れて行って下さい、本部へ、…お願い神田兄さん」
きっと断られるだろうと思いながらも、半ば投げやりにせがむ。
しかし意外にも予想していた言葉はひとつも聴こえて来ないまま、久しぶりに聴く日本語だけが耳を撫でた。
「遅えんだよ」
早く準備しろ、と神田が不機嫌そうに告げる。
「え、あの…」
「最初からこうするつもりだった。だけど、しっかり実を結ぶかどうかは」
神田に背中を押されて来た道を戻る。
は神田の回りくどさに苦笑した。
ヒグラシが鳴いている。梢が木霊していく。
じわりと陽に照らされる首筋に熱が浮いた。
これで、アメンボのワルツはもう 見れない。
07-09-05
(大事なのは世界の大きさではなくて)