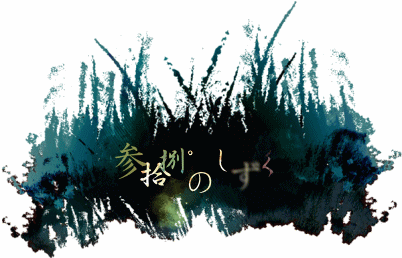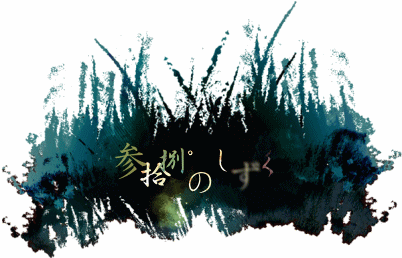
申し訳ございませぬ。柔らかな声とともに、しゃらり、と微かに装飾具が揺れる。綺麗に結い上げた漆黒の髪がちらちらと燻る明り取り用の炎に輝いて、低く、向かい合う初老の武将に下げられた。それは、風ひとつない静かな夜の事であった。
「何、気にすることはない」
「いいえ。天下の趨勢危うきこの時にとんだご迷惑を.....信玄公」
「よ、律儀なことは良いことだが、儂への謝罪も礼も後で存分に聞いてやろう。早くおぬしの主君の許へ向かうが良い.....そのために奥州から、急ぎに急ぎ、やって来たのだろう。」
ゆるりとひとつ瞬きをして、は薄く微笑んだ。本当なら、この程度の謝罪で済まされる恩義ではないが、目の前でじつとこちらを見つめる信玄の言うことは正しい。この老人はきっと私のすべてを見透かしているのだろう。もう一度だけ静かに頭を垂れて、はそっと信玄の前を後にした。襖を閉めて、そっと前を向くと、の耳飾りが微かに揺れる。じりじりと両腕が痺れている。両足も背も酷く痛む。だが、早馬に乗ることさえ滅多にない体で三頭を乗り潰して甲斐に来たのだ、むしろこの程度で済んで良かったと思うべきであろう。は物音ひとつしない廊下をつらつらと進んで、言い伝えられた襖の前で立ち止まる。微かな隙間からは、綺麗な上掛けの着物が見えていた。そっと襖に手を掛けて、僅かに力を込めると、するすると音もなく襖が開く。背後から差し込む月明かりが部屋を照らし出す様を、少しの間、はぼんやりと眺めていた。それから、思い出したかのように部屋へと踏み込む。優しい畳の感覚を味わいながら、静かに寝息を立てる自身の主君の枕元へと膝を揃えて腰を下ろすと、無意識のうちに、痛む腕は眠る男の髪を撫でた。緩やかに、見慣れた鋭い瞳が開かれる。
「...何でお前がここにいる」
「......傷は痛みますか」
「、質問をしているのは俺だ」
ぐ、との腕を強く掴んで、政宗はじつと目の前の女を見つめた。煌々と月明かりに照らされる眼が、音もなくに答えを強要する。掠れた声の余韻がすべて月明かりに溶かされる頃、ようやく、そうっとは唇を、動かして音を並べた。耳飾りの色鮮やかな宝玉が鳴る。じりじりと、掴まれた腕が痛んだ。
「あなたが、お倒れになったと聞いたからよ、政宗」
「随分と、早い到着だな」
「それは.....それなりに、急ぎましたから」
「そうかい」
政宗はそれきり、うんともすんとも言わなかった。恐らくは痛みを与えてしまうほどに、強く掴んだの腕が、酷く張って疲労していることで、政宗はどのようにしてがこの場所に座っているのかを大方理解していた。腕を掴まれたまま、じつと視線を落としていたの耳元で、しゃら、と再び宝玉がなく。
「よくぞ、ご無事で」
ぽたり、静かな声を追って続いたのは、揺れた耳飾りの音ではなかった。の腕を掴んでいた政宗の指先がぴくりと僅か怯んだけれども、しかし次の瞬きの前には、今一度、とても強い力が込められる。ゆっくりと半身を起した政宗は、それを制止しようとするをぐいと自身の肩口に引き寄せた。そうして、あやすようにの背中を叩くと、はぼろぼろと大粒の涙をこぼして政宗の胸に顔をうずめる。
「安心しな。おまえが心配するようなことは何ひとつねえ」
微かに笑いを含んだ政宗の声の後には、ひとりの女の嗚咽が響くばかりで、他には何の音もしなかった。けれども、政宗はそれ以上何も言わなかった。沁とした部屋の中を、緩々と、流れる雲の影が這っていく。庭先では、数匹の蟋蟀が鳴いている。政宗はしばらくの間じつと腕の中で感情を零す女を見つめていたけれども、が泣き始めて何度目かの瞬きののち、静かに微笑んで、目を閉じた。それは、風ひとつない静かな夜の事であった。